こんにちは、人機速報のyuです。
いきなり”無駄”とか強い言葉を使ってしまってごめんなさいね。
2025年現在、世界ではヒューマノイドの開発が大変盛り上がっており大手IT企業が次々と参入しています。読者の皆さんの中には、今から自分なりの哲学を持って人型ロボットで世界を取ろうという人もいるでしょう。そのくらい将来性のある市場であることは確かです。
そこで意欲的に取り組む技術者の助けになるべく開発にあたってハードルになるであろうことをまとめ、それぞれにどう対応すればいいのかまとめました。
1,資金問題
資金問題は重要です。例えば米テスラは数十億ドル、日本円にして数千億円から1兆円規模の投資をしているとされています。同様に中国のunitreeは数百億円規模、米Figure AIは約1,500億円などの資金調達を実現しており、巨額の費用が開発に投じられていることがわかります。
その結果として大手企業は優秀な人材を大量に雇い、質の高い製品を生み出し、技術開発を進めて市場にはない優位性を獲得できるというわけです。日本にいる技術者がここまでの資金を獲得することはそう簡単なことではないでしょう。
では勝ち筋はないのかといえば、現状いくつかの選択肢は残されています。
資金問題解決策 ローコスト戦術
皆さんは米テスラが売っているOptimusの定価をご存知ですか?約400万円です。これを高いと見るか安いと見るかはさておき、まだ改善の余地はありそうですよね。例えば初期のコンピューターは非常に高額でした。そのころ日本のメーカーが半導体やコンピュータ部門では世界を席巻していましたが、多少耐久性を下げても廉価性を確保する世界の新規参入者たちにその座を追われてしまいました。そしてコンピュータの価格は下がり、人々の手に届くようになったわけです。
日本が立場を追われたこの反省から活かせることは2つ。一つは価格優位性を担保する算段ができれば巻き返しのチャンスは十分にあるということです。一般的な家庭を想定しても、あるいは大量納入が見込める国や自治体、中小企業にしろ価格が低くならなければ手を出しにくいのは想像に容易いと思います。
そしてこの最終的な価格という側面では資金の少ない開発者にもまだ勝ち筋があります。
まず一般にIT人材の人件費は高く、優秀なプログラマーを雇っておくのには大量の資金が必要となります。ここで一つ、中国UBTECH ROBOTICSの決算報告(2024)からどれぐらいの資金が人件費に使われているのか見てみましょう。
結論:6.95億元。日本円にして146億5千万円/年使っているようです。しかもその金額は増加傾向。当然、資金調達で賄えない分は価格に転嫁することになるので、販売価格は材料や部品の原価というよりは開発費の比重が高くなります。最終的な価格が数百万円の規模になるのは当然と言えるでしょう。
また、別の側面からも高価格になり得ます。巨額な資金を当てにして開発を進めてくると、当然のように高性能で高額な部品を使ってしまうことになりがちです。ここで問題になってくるのが、価格を低くしようとしたときに高額ハードウェアに依存する部分の部品の費用を下げられない、もしくは相応の手間や時間がかかるということです。はじめから低コスト重視で開発を進めている(もしくはせざるをえない)開発者からすれば、そもそもの機体は比較的安いわけですから、完成できたとしたら低価格で提供できるわけです。
ローコスト戦術のメリット・デメリット
一旦ここまで出たメリットをまとめましょう。
| メリット |
| ・人件費を抑え、低価格でロボットを提供できる。 ・ハードの不足をソフトで補えれば、やはり低価格でロボットを提供できる。 |
では想定されるデメリットを見ていきましょう
ローコスト・デメリットA_開発が遅れる
開発者や技術者を雇えないわけですからこれは自然な流れです
ローコスト・デメリットB_プロジェクトが潰れる
これは一番回避しなくてはいけないものですね。
ここで一度、ローコスト戦術の「メリット」と「デメリット」を整理してみましょう。
| 観点 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 資金 | 開発コスト・人件費を抑えられる | 資金不足により開発が遅れる |
| 技術 | ソフトウェアでハードを補える柔軟性 | 高性能部品を使えず性能面で見劣りする可能性 |
| 組織 | 少人数で意思決定が早い | 経営基盤が脆く、プロジェクトが頓挫するリスク |
この中で「デメリットA」にあたる「開発が遅れる」という点は、必ずしも悪いこととは言い切れません。
たとえばGoogleが検索サジェスト機能を開発していた頃、競合企業のほうが人員も資金も圧倒的に多かったにもかかわらず、最終的に世界を制したのはアイデアと設計思想で勝負したGoogleでした。
また、自動車産業でもフォードが先発であったのに対し、後発のトヨタは生産方式の工夫によって今では世界を代表するメーカーとなっています。
ヒューマノイド産業もいずれ自動車産業と同じように巨大市場へ成長すると予想されます。つまり、後発であっても勝機は十分にあるのです。むしろ、先発企業の失敗や課題を分析し、それを回避できる立場にあるという点で、後発は有利とも言えます。
一方で「デメリットB」、すなわち「プロジェクトが潰れる」という事態は、何としても避けなければなりません。開発のスピードが遅くても、続けられればまだ希望がありますが、資金が尽きて終わってしまえばすべてが水泡に帰します。したがって、大手の巨額な投資額に目を奪われるよりも、自分のペースで確実に進められる体制をどう維持するかに焦点を置くべきです。
さらに私見を述べると、ヒューマノイドが「人間に近づく」ほど、その開発は倫理的な問題と向き合うことになるでしょう。人格の定義、行動の自由、ロボットにとっての「正義」とは何か──そうした問いに対して、大手企業では資金提供者や株主、法務部門など多層的な利害関係が絡み、合意形成が難しくなる可能性があります。
その点、小規模な開発チームは関係者が少ない分、思想や価値観を共有しやすく、意思決定も迅速です。人格や文化を反映した個性的なヒューマノイドを生み出すうえでは、むしろ偏りのない“中庸”よりも、明確な世界観や哲学を持つ少人数のチームのほうが有利な場合さえあるでしょう。もちろん、常識と倫理を欠いてはならないことは言うまでもありませんが。
小規模チームが取るべき具体戦略
では、限られたリソースの中で小規模チームがどう立ち回るべきか。ここからは、現実的な戦略をいくつか考えてみましょう。
1.「一点突破型」の設計思想を持つ
まず大切なのは、すべてを作ろうとしないことです。
大手企業は人材も資金も豊富で、機構・AI・通信・センサーなどを総合的に開発できます。しかし、小規模開発では「一点突破」が鍵となります。
たとえば、特定の関節構造、手指の繊細な制御、または人との会話に特化した自然対話AIなど、「一つの分野で世界一を目指す」という設計思想が重要です。その一点を他社が真似できない水準に磨き上げることで、連携・OEM・買収など、次のステージへの道が開けます。
2.「ローカル特化」の発想で生きる
もう一つの戦略は、グローバルではなくローカルを狙うことです。
たとえば高齢化が進む日本では、家庭用や介護支援用のヒューマノイドに特化するほうが現実的です。農業や観光、教育など地域密着型の課題は数多くあり、大手が参入しにくい細分化市場こそ、小規模開発の舞台になります。
実際、海外の多くのスタートアップは、自国の文化的・社会的文脈を背景に、限定的な機能をもつヒューマノイドで成果を上げています。日本でも同様に、「地域に根ざしたロボット」の価値を見直すべき時期が来ています。
3.「共創」ではなく「共鳴」を狙う
近年の開発では、共同研究やクラウドファンディングなど「共創」という言葉がよく使われます。しかし、小規模開発勢が生き残るためには、単なる協力関係よりも「共鳴」──つまり哲学や思想の共感を軸にした連携が求められます。
同じ価値観を共有する技術者やアーティストと手を組めば、資金や人員を超えた創造的な力が生まれます。逆に、目的の違う企業と無理に組めば、方向性がブレて消耗戦になるだけです。
4.「技術」よりも「物語」を語る
そして最後に、開発者自身が物語を語る力を持つこと。
ヒューマノイドという存在は、人間の夢や恐れ、希望といった感情と密接に結びついています。だからこそ、スペックや性能よりも「なぜ自分は人型を作るのか」「どんな未来を信じているのか」を語れる人が強い。
資金も設備も限られていても、理念とビジョンが伝われば人は集まります。実際、世界の多くのロボット・スタートアップが、最初はたった数人の情熱から始まっています。
これからのヒューマノイド開発は、資本の戦いだけではありません。
「どんな社会にしたいか」「そのために人型という形をどう活かすか」という問いに、誠実に向き合える小さなチームこそが、次の時代の扉を開く鍵を握っているのです。


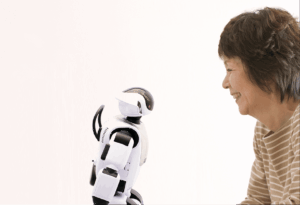
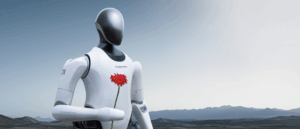
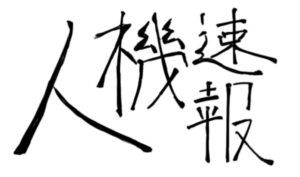
コメント